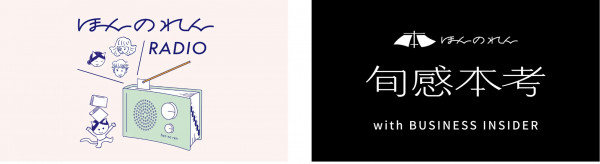|
海辺の連想遊び
6歳のある夏の日のこと、ここだけ瞬間冷凍したように今でも妙に鮮明に思い出される半日の記憶があります。家族で訪れた海辺で、金色の髪をした男の子がひとりで遊んでいました。あまりの髪の色の美しさに目を取られていると、視線に気がついたのか、私のところにやってきて手の中の貝殻を見せてくれました。私はドキドキしながら、ポケットに大事にしまってあった黄金虫の死骸を見せました。すると少年はパッと顔を輝かせて両親のところに走って戻り、七色に光る陶器の破片を持って戻ってきました。
隣同士に並べると、陶器の欠片と黄金虫の羽の色がそっくりです。顔を見合わせて笑い、砂浜の中に光る石や貝殻を探し始めました。似た色のものを見つけては集め、集めたものを形で分けては、今度は似ている形をしたものを集めてくる。石も貝も葉っぱもゴミも、なんでもありです。同じような色や大きさや形のものを持ち帰って似たもの同士を並べては、時折一緒に笑い転げ、時折無言のまま砂浜をはいつくばる。そんな遊びが少しの途切れ目もなく続いていきました。
もう行くよと呼びに来た母に「言葉が通じないのによくこんなに遊べるわね」と言われた時はじめて、「言葉が通じていない」ことに気がついたのでした。次から次とお互いの発見を並べていくだけで、延々と遊んでいられたのです。
「似ている」ものを次々持ち合うというだけで、どうしてこんなに夢中になったのか。思えば言葉に頼れないぶん、互いのやりとりを面白くする微細なルールが自然と生まれていました。相手が見つけたことを引き取ってちょっと加える。後には戻らず先に先に進む。形、色、大きさなど、つぎつぎと「連なり」のルールを渡り歩いていく。この連想遊びは、追いつ追われつの鬼ごっこのようでもあり、ふたりで力を合わせる積み木のようでもありました。
江戸の「連」、連なるという方法
日本には、大人を夢中にさせる「連なり」の遊びが古くからありました。最たるものが「連句」です。連句には、「去嫌(さりきらい)」(同類の語は一定の句を隔てないと使ってはいけない)や「月花の定座」(月と花はよむ場所が決められている)といった実に精緻な式目(ルール)が敷き詰められています。この「縛り」によって、前の句と同じ句にも別の句にもならないよう「付かず離れず」のテンションを互いに守りながら「連なりの世界」を出現させていきます。
連句は、中世貴族の遊びであった連歌が、俳諧(滑稽)の色を加えて庶民に広がったものです。その場の宗匠と呼ばれる仕立て人が「五七五」の「発句(最初の句)」をつくると、次の者が「七七」をつけ、その後に「五七五」さらに「七七」と即興的に連ねながら、最後の「挙句」まで続けます。今ではバラエティ番組ですっかり人気の「俳句」は、江戸後期から明治にかけて連句の発句が独立して詠まれるバリエーションとして登場したものです。それまで句といえば連ねて読む連句が主流で、基本的には複数の人々によって時と場を同じくして作られるものでした。
江戸時代には、この連句などを遊ぶ「連」と呼ばれるサロンが都市部のそこかしこにありました。職業の領域を超えて人が集い、さまざまな創作活動が発露した経済文化サロンです。松尾芭蕉、井原西鶴、伊藤若冲、与謝蕪村、葛飾北斎、杉田玄白、蔦屋重三郎……、これらの才人たちは、みな「連」によってその才能を開花させていきました。俳諧や浮世絵や落語から、博物学や医学まで、その後の日本の生活文化や経済文化の礎となる多彩な価値が、連から創発していったのです。いったいなぜ、「連」という場にはそうした力が漲ったのでしょう。
江戸文化研究者の田中優子さんによれば、江戸の「連」は、西洋におこったサロンときわめて近いものの、人と場の関係において決定的に異なる性質のものだそうです。日本の「連」は、完成された個人がいてその集まりとしてのサロンがあるのではなく、「場」のなかでいかようにも変化しうる「未完の個人」が場の一部となって成立するのだと言います。
場をつくる個・場にひらく個
しかしながら、大人が遊ぶ「連」のような場は、江戸を最後に見られなくなったと言います。
“(連のような)場は個人の次元とは異質な次元をつくりだすので、個人であることに固執する者はいない。近代になって場が消滅するのは、場における相関的な個ではなく、無条件で絶対的な個に、より高い価値が置かれたからである。 ”
『江戸はネットワーク』田中優子(平凡社ライブラリー)
連にあった「場のダイナミズム」は、西洋的な個人主義では解けない現象のようです。人の集まりとしてのサロンではなく、ある動的な生成の勢いを共に生み出すような場では、個人は他者や共同体に一体化するのではなく、むしろ他者と離れながらあくまで連なる、という特徴を持っていました。
おそらく連の人々は、句や物語などの何かに事寄せては相互に才能を引き出しあい、想像力を自由にする風をお互いに送り合うような連なり方をしていたのでしょう。共創の成果のみならず、むしろそのプロセスにこそ価値を置くような連なり方です。松尾芭蕉は連句の教えとして「文台引き下ろせば即反故也」と言いました。文台は連句を認める懐紙を乗せる机のことで、つまりそれを終えてしまえば書かれた連句は反故(ほご:捨てて良い紙)である。出来上がったものよりもそこにいたるプロセスこそが、「連」という場の作品なのだという意味です。
独立し閉じた個人としてではなく、半ば場に対してひらかれた才能の芽吹きとして、どんな発露も歓迎された場だったはずです。そうした場には常に、才能を入れて交わらせるに足る器がありました。歌や本、絵画や物語など、「事寄せる」何かが媒介となり、江戸の文化は爛熟期に入っていきました。
本の連「ほんのれん」
現代の組織やコミュニティの中にも、「連」のような「未完の個」の才能を引き出し合う小さな場を創り出すことができないか。「一畳ライブラリー『ほんのれん』」は、そうした願いから生まれた装置です。
毎月更新の一畳ライブラリー「ほんのれん」(丸善雄松堂・編集工学研究所の共同事業)。毎月「問い」と5冊の本とワークノートが届く、場の創発装置。
「ほんのれん」は「本の連」。何に「事寄せる」かと言えば「本」です。本を媒介にして対話をすると、日頃は伏せられた関心や感興が、不思議な程にお互いのあいだに湧き出してきます。企業や地域コミュニティや学校の中に、本を媒介にして「内なる未詳の感」(連編記vol.2より)が交わされうる小さな場を出現させたい。江戸の「連」にあったような、他者と離れながらあくまで連なる創発の場を、本の力を介してそこかしこに生み出していきたいと願うものです。
「連なる」ことがそのまま遊びになった子どもの頃の、柔らかく場にひらいた「未完の個」としての「私」を、時折呼び戻してみてはいかがでしょうか。
安藤昭子(編集工学研究所 代表取締役社長)
◆千夜千冊・書籍 ご参考:
|


![HYPER EDITING PLATFORM [AIDA]](/images/common/side_bnr_logo.svg)