編集と問いが未来を切り拓く―『問いの編集力』出版記念 佐渡島庸平×安藤昭子対談レポート
編集工学研究所代表の安藤昭子の新刊『問いの編集力』の出版を記念して、株式会社コルク代表で編集者の佐渡島庸平氏とのトークイベントが「コルクラボ」で開催された(2024年11月)。AI時代が到来し、ビジネスの現場でも課題解決力よりも課題発見力が重要とされる現在、「問う力」はどのように培うべきなのか。「問う力」と「編集力」をテーマに語った。

松岡正剛がつないだ縁
佐渡島庸平(以下、佐渡島):編集工学研究所が主催し松岡正剛さんが座長を務めた塾(Hyper-Editing Platform AIDA)に、僕は受講生として通っていたことがあります。松岡さんの生の声を聞いて、編集とは何かを考えたいと思ったのが、塾に通い出した理由です。ただ、松岡さんは編集を通してどんな社会を実現したかったのか、そこが分くわからないままでした。
今回、『問いの編集力』のゲラをやり取りしている途中で、残念ながら松岡さんが亡くなられたというニュースが飛び込んできました。松岡さんが抱えておられたであろう問いの中身が、結局分からないままになってしまいました。
今日はそのあたりも含めてお話を伺いたいのですが、安藤さんは、松岡さんから問いを持つことの大切さをたくさん教えられてきたのではないでしょうか。
安藤:そうですね。まず松岡正剛の問いは、常にビッグクエスチョンです。「どういう社会を実現したいのか」といった今の社会を最適化するような範疇を超えているのだと思います。よく日本は中空構造(中心に空間や空白を持つ構造のことで、神社建築などに見られる日本的な特徴)だと言われますが、神社も真ん中は空っぽで、そこに神様がいらっしゃるという作りをしています。松岡さん自身がこれに似ていて、関心の真ん中は空洞な感じがするのです。強いて言うならば、「この世界はどうなっているのだろうか」ということに対して、ひたすら好奇心があったのだと思います。

大きな「問い」を持ちつづけること
安藤:『知の編集工学』という本の中に、松岡さんが若い頃に設定した七つの問いがあります。「なぜ自然は階層性を持つのか」、「なぜ人間は自己を持ち得たのか」、「なぜ生命は相互作用に入っていくのか」といったそうそう簡単には解けないような問いばかりです。
20代の頃からこうした大きな問いを持ちつつ、ずっとそれを更新し続けてきたのだと思います。その過程で「そうか、この世界は情報を編集しているのだと見れば、ほとんどのことが解けるのではないか」と思ったのでしょう。その気づきが、「編集工学」につながっているのだと思います。
松岡さんはいつも、僕は、編集を終えようとしている世の中に抵抗しているんだと言っていました。人間が「作り終えたよね」「これでいいよね」とするものに対して、「本来の生命はこんなに生き生きとしているじゃないか」、「歴史はもっと今に届く複雑さを持っていたじゃないか」といったように、「そういうものだ」と済まされようとするものに対して、ずっと抵抗し続けたのではないかなと思います。
佐渡島:松岡さんは問いのサイズは、世間と大きく乖離していますよね。社会から期待されている行動と、自分の好奇心の自由さ、興味のあり方に、相当なギャップがあるだろうから、どうやってバランスを取っていたのだろうとすごく気になります。
安藤:一つには、松岡正剛は俗世間からは遠そうな深淵な問いを抱えていながら、一方では現場仕事のプロフェッショナルであったということです。お客様が相談にいらしたら、その人のために何をしてあげたらいいかを、松岡の編集力でもって提案するわけです。仕事人として、大工の棟梁のようにプロフェッショナルだということが一つです。
もう一つは、松岡さんは現実社会で起こっていること、例えば、コンビニの新商品とか、ドンキホーテで売っているつけまつ毛の種類とか、そういうことにものすごく関心がありました。晩年は「世界と世界たち」という言い方をよくしていましたが、世界というのは、深淵なる七つの問いに代表されるような、ある種の普遍性を持った世界。一方で「世界たち」は、ものすごくささやかだったり小さかったり、いろいろな姿をしているもの。その二種類がある。そしてこの「世界たち」の方からしか、文化は生まれないと見ていたと思います。
本人はバランスを取っているつもりは一切なかっただろうけれど、深淵さと今刻々と起こっていることの両方で生きている人だったのだろうと思います。
優れた編集者は「中空的」である
佐渡島:編集という仕事自体も、本来が中空的というか、先に自分の意思やしたいことが強くありすぎると、行き詰まりやすくなると思うのです。
僕も編集者なので、この作家が何をしたいのか、この作家はどうありたいのだろうかと、ある種憑依するような感じでなりきって、作家には漫画を描く、小説を書くだけに特化してもらうように心がけています。その憑依力を強くしようと思うと、自分が中空的になるのです。
昔先輩から、本当にいい編集者は、右翼からも左翼からも最も信頼される人だと教わりました。その感じが中空感というか、ブラックホール感があると感じます。
安藤:松岡さんもまさにそういう人。というのも、方法こそがコンテンツだという考え方なのです。右翼的とか左翼的とかっていう思想やコンテンツが先にあるのではなく、そこにどんな方法があるのか、どうすると面白く見せられるかというところを見ていると思います。トピックとかテーマは、「方法」が動くための素材なのです。
「中空である」というのは、真ん中に先に自分の主張やテーマがあるのではなく、編集という営みを通して主題が生じてくるということだと思います。
もう少しだけ言い変えると、「主語よりも述語的である」ということ。編集者の仕事は、とかく述語的なのだと思います。主語がどこかにあって、自分自身は述語でどうとでも包んであげられるというような。それを極めていくと、自分自身が変幻自在なので、なんでも扱えるようになります。
「編集」とは何か
佐渡島:では、ここから『問いの編集力』の話に。まず「編集」とは何なのかを考えてみたいと思います。
よく作家はゼロイチを生み出して素晴らしいと言われますが、僕はそうは思っていません。創作物自体は素晴らしいのですが、それもゼロイチではないと思っています。
いかなる場合でも、作家が過去読んだものが作家の中で編集されて物語として紡がれているのであって、作家の中から急に生まれることはないのです。世の中の全ての物事は、編集されていると言えてしまう。
安藤:私たち編集工学研究所は、ものすごく広い意味で「編集」という言葉を使っています。情報を扱う営みは全部「編集」だと言えます。ただしわたしたちの編集力は、多くの部分が周囲との相互作用の中にあります。
例えば、喉が乾いたなと感じて、ペットボトルを持って水を飲もうとしても、私の頭が全ての位置を計算して、手の形を決めて、主体性だけでペットボトルを掴めるわけではないのです。アフォーダンス(環境が人間に働きかける行動可能性のこと)という考え方がありますが、情報(ペットボトル)側がまず意味を持っていて、私に対して「手の形はこう」と誘っているわけです。
何かの情報に出会って、それを自分なりにもっと面白くしたいとか、もっと自由に考えたいと思う時に、編集が起こります。先ほどの主語と述語の話で言えば、あまりにも主語を大事にしてしまうと、「ペットボトルとは」、「水とは」から始めるので、このペットボトルを面白くするというアイデアが動きにくくなります。
ゼロイチで新しいものが生まれるのではなく、連綿と続いている文脈の中で、さまざまなものをもらいながら、あたかも新しいものができあがったかのように見える。文脈を使いながら述語的に手伝いをしているのが、「編集」なのだろうと思います。
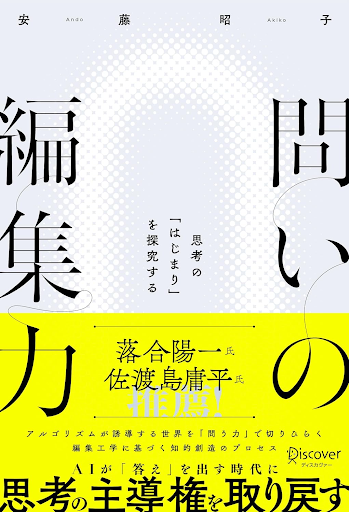
頭の中のフィルターを外して、述語的に考える
佐渡島:同じものでも違う可能性でものを見てみると、それが驚きや問いになります。「これは水だ」と決めつけてしまうと、そこに驚きは生まれない。
安藤:驚く能力は間違いなくAIにはなく、人間が持っている力ですよね。ここでいう驚きというのは、「あれっ?」と思う驚きのことです。いつも見ている景色だけれども、「あれ?何でこんな形なの?」と思うことが重要です。
私たちの頭の中には、簡易的に理解をするテンプレートができているわけです。そうでないと、目にするすべてのことに頭を使わなければいけなくて大変です。そのテンプレートやフィルターになっているものを自覚して、あえて一度外してみる。そうすると、「あれ?」という問いが生まれるのではないかなと思います。
AI時代は、AIにどう問えるかが大切
佐渡島:ただ、AIに聞いたときに返ってくる答えはすごいですよね。今のAIはしっかり問いを立てていくと、むちゃくちゃサポートしてくれます。やはりAIの時代は、どうAIに問うていくのかなんだなと思うんです。
安藤:私もそのことよく考えています。ある時ChatGPTに、AIは問うことができないという前提で「今一番あなたが関心のある問いはなんですか」と聞いてみました。少し前のChatGPTだったら、「私はAIですから、問いは持ちません」という答えが返ってきましたが、今は、「あなたといかに楽しく話せるかということが、今の私のもっぱらの問いです」という答えが返ってきて。逆に私にいろいろ問うわけです。「あなたはどうすると快適ですか」などと学習しようとする。
佐渡島:記憶してくれますからね。
安藤:そういう時代において人間が人間たる尊厳を手放さず、生きる意味を見失わずに生きるためにも、自分の中から説明もつかないような問いが湧き続ける状態にしておくのは、とても大事なことではないでしょうか。『問いの編集力』を書こうと思ったきっかけも、そこにありました。
「やりたいこと」を軸に問いが発生する
佐渡島: AIと人間の違いは、人間には「やりたいこと」があり、やりたいことを軸に、問いが発生してくることではないでしょうか。例えば、僕が松岡さんを知りたいということも、大本としては編集をよく知って、理解して、それを自分の仕事に使いたいという思いがあるからです。
安藤:松岡が編集していた雑誌『遊』には、「相似律」という有名な特集がありました。なにかというと、ただひたすら似ている写真を集めていくのです。例えば、象の皮膚のシワとガラスのひび割れと蜘蛛の巣の写真を並べて載せて、「ほら、似ているでしょ」というような。『問いの編集力』の中にも出てくるグレゴリー・ベイトソンは、世界を繋がり合うパターンとして見ると言った人なのですが、松岡さんも非常にベイトソンには影響を受けていたと思います。世界の中にあるパターンを見つけてきて発見した時の喜びをとても大事にしたんです。

出会い頭でしか生まれない創発性を大切にする
安藤:『知の編集工学』に、「編集的創発性」という言葉があります。世界の創発、相転移にあたるものがとても面白く、非常に可能性を感じていると。出会い頭でしか生まれてこない、それまで伏せられていて、何が出てきてもおかしくない「別様の可能性」を作りたいと書いています。
私も『問いの編集力』では、読者のみなさんと一緒にこの「創発」を起こしたり共有したりしたいなと思いながら書きました。
佐渡島:問いによって、創発を生み出せますからね。
安藤:分かったと思う状態が、一番止まっている状態。知れば知るほど分からないことが増えていく状態を作るなかで、自分でも思いもかけないようなことが生まれてくるのが「編集的創発性」です。
佐渡島:僕はいろいろな人と創発的な会話をしたいと思って、問いをよく投げかけるのですが、そうすると「圧がある」と言われてしまいます。そこでChatGPTに、「問いを一切使わずに対話をしながら創発する方法は何ですか」と質問をしたんですよ。
安藤:相当高度な相談していますね。
佐渡島:ChatGPTからはしっくりくる答えは出てきませんでした。自分で考えたのは、問いをもっと小分けにして聞くといいだろうということでした。
安藤:おっしゃるとおりで、ど真ん中の問いでは、編集は案外動かないものです。何かを言い換えたり、見立てたり、ずらしたりすると、相手の頭の中のイメージも動きやすくなりますね。
「ゆらぎ」をもたらすマイクロスリップ
佐渡島:『問いの編集力』の中で、僕はアフォーダンスとマイクロスリップについての部分がすごくいいなと思ったのです。「演劇の世界でもマイクロスリップはキーファクターになっている。人がうまいと認識する役者は無駄な動きを適度に入れている」と。
安藤:ペットボトルを例にすると、人はペットボトルを掴むのを意識はしていないけれど、一度で一番いい場所は掴めていないのです。少しずつ直しながら持っているのです。例えば、コーヒーカップを持つ時に、何度もNGを出しているうちに、一番いい場所をいきなり掴めるようになってしまうけれど、それは人間の自然な動きではないわけなのです。その無駄な動きを常に人間はやっているので、無駄な動きごと再現できている役者さんが、実はうまい役者さんだという。
佐渡島:それがリアルということですよね。台本があるとやることが明確だから、一直線になりすぎるのでしょう。新人の漫画だと、作者が伝えたいことだけを登場人物みんながやっていて、無駄な動きがない。物語と関係ないものを手に持っていたり、動作をしていたりするとリアリティが高まって、キャラクターらしい行動が増えていくものなのです。
安藤:情報は本来、ゆらぎがあるもの。人間が上手にやろうと思うと、よかれと思ってそのゆらぎを排除してしまう。それは漫画も役者さんの動きも組織の作り方も全て関係してくるのではないかと思います。無駄や余白、ゆらぎをいかにいい具合に持てるかは、いろいろな場面で大事ですね。
組織やプロジェクトにおけるマイクロスリップとは
佐渡島:演技だとマイクロスリップ的なものがあった方がいいというのは分かっても、こと組織やプロジェクトとなると、明確に意図があって一直線にやりたくなってしまいますよね。そういうものにおけるマイクロスリップ的なものは何なのか。
安藤:プロジェクトの中では、一見無駄だとか遠回りだと思うことに取り組む勇気が大事です。一度勇気を出して迂回する道を作れば、そこに回路ができます。回り道した方が結局は早いということは、体験値になっていくと思います。最初にその勇気を出す人がいないと、私たちのやっている活動はどんどん合理化する方に進んでいってしまいます
佐渡島:『問いの編集力』は、どうやって見方を変えるかということを教えてくれます。何をもって総合的に見るのかを、どう変えるのかという話です。
安藤:フィルターを意図的に外せるか、その状態に常になっていられるか。結局はそれに尽きると思います。それさえできれば、いつもだったら驚けないことに「おや」と思うのは、そんなに難しいことではないはずです。
「心配」や「不愉快」を、問いに変える
佐渡島:あともう一つ秀逸だと思ったのは、この部分です。
“いつだって「心配」と「問い」は紙一重だ。自分の内側で勝手にグルグルまわりを続けるブツクサを、どこかで区切って「じゃあどうしようかな?」と思ったとたん、「不安と混乱」は「好奇心と問い」に変わることがある。今この瞬間にも忙しなく動いている注意のカーソルを自在に操縦し、世界をあるがままに受け入れながら、不安や混乱を飼いならすのだ。それが、次の好奇心と問いのタネになる。”(p75)
僕自身、10代、20代の時からすごい心配症で、いい作家と仕事をしていると信じられないぐらい心配症なるのです。でも、昔からその不安が面白い問いに変換する方法を知っていました。
自分が乗りこなせる難しさだと思うとワクワクに変わって、無理だと思うと不安に変わる。不安とワクワクは、同じ出来事に対して、こちらの能力とこちらの余裕が決めているだけのこと。だから、「心配と問いは紙一重」ということには、すごく共感します。
安藤:それはまさに私も強調したいところです。心配事や不安なことなど一見ネガティブなことも、ある程度は自分の中にあっていいんですよね。その上で編集力を身につつけることを、是非おすすめしたい。それによって、ストレスフリーになれるのです。不安なことも心配なことも上手にできないことも当然たくさんあるのは変わらないのだけど、編集力によって自由になれる。
編集は情報を扱うこと。相手が情報である以上、全部編集できるわけです。問いに変えるのも、ある意味で編集していることです。例えば、自分が直面している困難や心配事がありますが、それも全部情報である以上、どこかで編集できる糸口があるという確信さえ持っておけば、全て面白い問いに変換できるはずです。
佐渡島:心配とか怒りは、自分の心のセンサーなのであった方がいい。心配や怒りを感じると、外部に対して怒ったり攻撃したりすることがあります。でもそうではなくて、心配や怒りを自分自身で編集しにいくと、その状況が変えられて面白いことになる。
その成功体験があると、心配や怒りを感じた瞬間に、面白い感じになるというか。「不愉快」を「刺激」にして、面白い問いが見つけられる。心配や怒りの周りには、自分の人生にとって重要な問いが転がっている可能性がありますよね。
安藤:解決方法が1 種類だと思っていると苦しいですね。ある刺激を受けたことによって、普段見えていなかったことに気がつくこともあります。それを自分の好奇心に変えてしまうと、イラっとすることがあったとしても、「そういう一面もあるんだ」「へぇ」と思える。いろいろな抜け道を自分で設定できるという意味でもあります。
私たちが出会う場面や機会は、無数の可能性で膨れています。私も佐渡島さんも、今は座って話をしていますが、急に立ち上がって演説し始める可能性を私たちは常に持っているわけです。その可能性に目を向けることが、情報を編集することの一つではないでしょうか。
自分の中にある「問いの力」や「編集力」をしっかりと自覚すれば、そうした無数の可能性は、生きる上での大変豊かな資源になっていきます。
ありがとうございました。
(※)編集工学研究所のニュースレターでは、最新情報のご案内をお送りしております。以下よりご登録ください。
編集工学研究所 Newsletter

![HYPER EDITING PLATFORM [AIDA]](/images/common/side_bnr_logo.svg)







